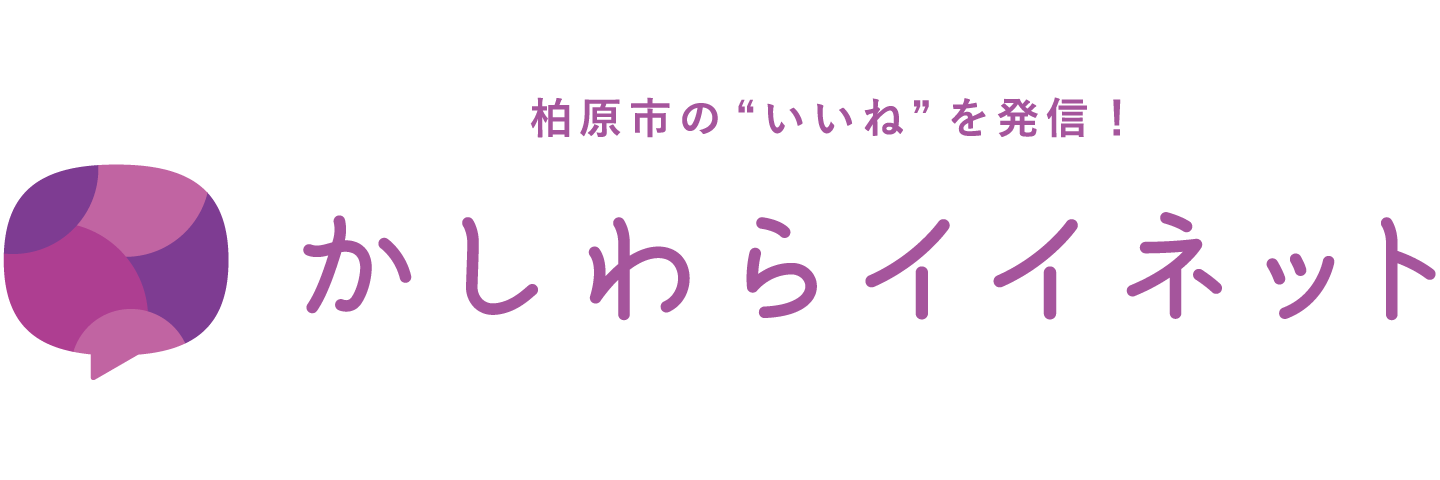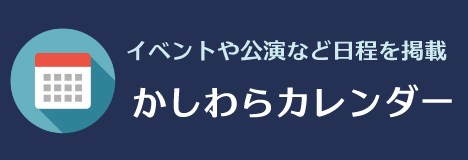笑う門には福来る。「笑いの絶えない人の家には、自然と幸福が訪れる。苦境にあっても希望を失わずにいれば、やがて幸せがやってくる」という諺(ことわざ)だ。ここで言う「門(かど)」とは「家・家庭」を指し、出入り口にある「門(もん)」の意味ではない。
1月28日、地元の柏原リビエールホールにおいて「桂文三 新春落語会」が開かれた。一席目は「宿替え」。長屋暮らしである夫婦の引っ越しを描いた噺(はなし)だ。隣と共有する壁に夫が八寸釘を打ち込んでしまったことから、滑稽な会話が繰り広げられる。
枕で 「私は柏原市に住んでおりまして」と、自らも長屋生活だった当時の暮らしぶりを、近所に居住していた人々の姿とともに語り、笑いを誘っていた。ひとしきり場をあたためたあと、文三さんは口にする。
「あの時、確かに生きてたな、と思うんですわ」
当時の生活にはプライバシーがなかった。人々の声が四方八方から聞こえてくる。笑いや喧騒、怒りや涙、周囲の喜怒哀楽。身近に住まう他人の悲喜こもごもが、日々の暮らしに詰まっていた。
電話があれば誰かが借りにきて、聴く必要のない話まで耳にしてしまう。近所の人たちの姿を目の当たりにし、生きることの現実に直面しながら、文三さんは育ってきた。
そこで培われた観察眼が、芸の基礎を築いている。単に滑稽で、面白いだけではない。「笑うことのできる ありがたさ」が、噺の根底にある。

身ぶり手ぶりにも実体験が活かされている。八寸釘の寸法と壁の感覚はもちろん、夫婦が暮らす長屋の状況も、かつての住環境が頭にあり、推しはかることができる。
「横に戸を開ける玄関から入って、上がると居間や台所、横には壁がある。家の間取りはもちろん、奥行きや幅の感覚が備わっているのは、今となっては私の財産ですわ」
母が嗜んでいた三味線にも影響を受けた。学生時代、文三さんは落語研究部に入って初めて三味線を手にした。その音色やリズムは幼少時から心と体に染みついていた。
現在と違ってリアリティのあった昭和の時代劇にも夢中になった。文三さんの「笑い」には自他含めた家庭環境や当時の文化が、心の奥底に根づいている。
本格的な落語家となるため、昭和の上方落語の四天王、五代目桂文枝の「一門」に入った。師匠にも苦労を強いられた暮らしがあり、その話芸に活かされている思うと、厳しい教えもそれほど苦にならなかった。
入門してから地道に演目を続け25年となった平成28年、第11回繁昌亭大賞を受賞。25年以下の落語家が対象となる最後の年に、大きな花が開いた。今回の新春落語会は、受賞記念も兼ねての開催に。
「この噺は、落語を好きな人ならよくご存知かと思いますが、演じ手が変わると噺の面白さも違ってくるんです。そのあたりもわかっていただけましたら」
二席目は「時うどん」。冒頭の男同士のやりとりなどは、文三さん独自の解釈と表現がなされている。
「これからは古典落語を追求しつつ、桂文三ならではの個性も出していきたいんです」
笑う門に「繁昌亭大賞」という福が舞い込み、ひとつの節目を迎えた桂文三さん。今後も自らのルーツと向き合いながら、新しい挑戦も忘れない。その笑顔のなかに輝くまんまるな眼は、さらなる先を見つめている。
(取材:おおむら)